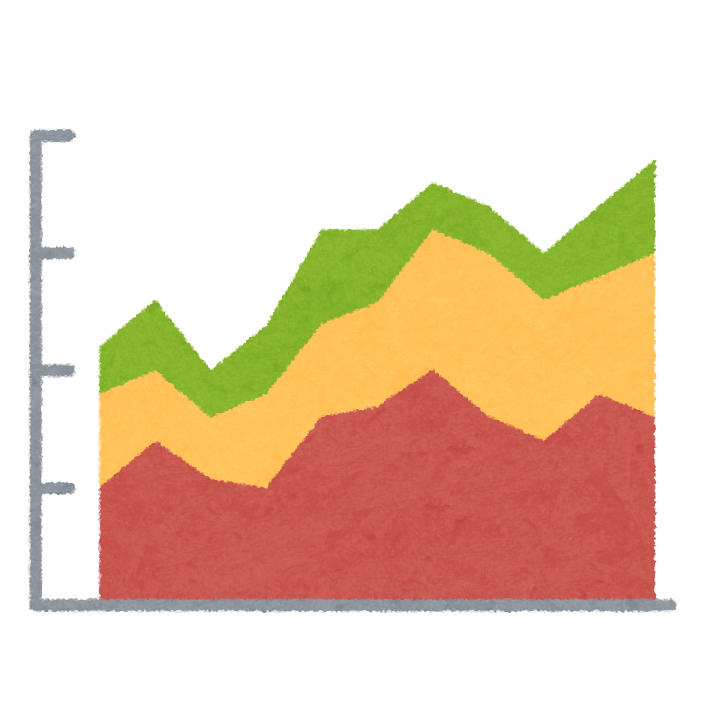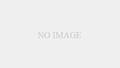日本国憲法について勉強すると、必ずと言っていいほど出てくるのが「三大原理」です。
「三大原理」が日本国憲法の土台となる大原則だと言われます。
そこで、このページでは
「日本国憲法の三大基本原理に注目しながら、憲法を読み解く際の2つの前提」
を確認します。
【日本国憲法の三大基本原理】
日本国憲法の三大基本原理と言われたら、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3つです。
この3つだけは絶対に揺るがない重要な内容のため、三大原理とされています。
それぞれの特徴を確認しましょう。
〈国民主権〉象徴天皇制と国事行為
名称の通り、国民が主権を持っているという原理ですが、これは「天皇主権でない」ことを同時に表しています。
そのため、日本国憲法では天皇を日本国および日本国民統合の象徴としています。
これを象徴天皇制と呼びます。
そして、天皇は国事行為のみを行うことになっています。
〈基本的人権の尊重〉侵すことのできない永久の権利と個人の尊重
どのような場合でも、基本的人権の尊重が保障されることになります。
そのため、基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」と表現されます。
ちなみに、基本的人権の尊重の土台にある考え方は「個人の尊重」だとされます。
〈平和主義〉前文・9条と「戦争放棄/戦力不保持/交戦権の否認」
日本は、恒久平和主義を採用しています。
また、憲法の前文で平和的生存権を保障しています。
さらに、憲法9条で平和主義を具体化しています。内容は、「戦争放棄/戦力の不保持/交戦権の否認」の3つをおさえます。
・国民主権の「参加のしくみ」まで確認する
→ 参政権/選挙・国民投票・住民投票について
・基本的人権の「最初の柱=自由権」から押さえる
→ 自由権の3分類と精神の自由の判例
・平和主義を「現実の安全保障」まで一気に整理する
→ 日本の平和と安全保障(憲法9条・自衛隊・日米安保)
【日本国憲法の前提①(最高法規性)】: 憲法尊重擁護義務と「誰を縛るのか」
〈憲法は国の最高法規〉
日本国憲法の前提の1つに、最高法規性というのがあります。
これは「憲法は国の最高法規である」という当たり前の話なのですが、ポイントは「最高法規なので憲法尊重擁護義務を負う」ということです。
つまり、憲法は必ず尊重しなければならないくらい重たいものであるということです。
〈憲法尊重擁護義務を負うのは誰か〉国家権力と国民のちがい
では、この憲法尊重擁護義務は誰が負うのでしょうか。
注意したいのは、憲法尊重擁護義務を負うのは国家権力であり、国民は憲法尊重擁護義務を負わないという点です。
つまり、「憲法は国民ではなく、国家権力を縛るものである」という点が憲法を理解する際の大前提です。
【日本国憲法の前提②(憲法の性質と改正手続き)】: 硬性憲法と解釈改憲
〈憲法の性質〉硬性憲法と解釈改憲(自衛隊をめぐる議論)
日本国憲法の前提のもう1つに、硬性憲法というのがあります。
これは「法律の改正よりも手続きの要件が厳しい」という意味です。
法律よりも改正までの手続きが硬いから、硬性と名付けられています。ただし、憲法の改正が難しいとなると、いくつかの論点も登場します。
代表的な例が自衛隊です。
先ほど、日本国憲法の平和主義で第9条に「戦力の不保持」があることを確認しました。
自国の平和維持のためには自衛隊は必要だと言われますが、自衛隊は戦力にあたらないのでしょうか。
つまり、「自衛隊は違憲なのではないか」という考え方が出てきたわけです。
この問いに対する日本政府の答えは「自衛隊は戦力ではなく日本を守るための必要最小限度の実力である」です。
実力なので、戦力にあたらないそうです。
このように、憲法の文章を改正せず、憲法の解釈だけを変えて対応していくことを解釈改憲と言います。
現在の日本は、硬性憲法なので解釈改憲で対応しているというわけです。
このように、解釈改憲には「憲法の条文を変えなくても現実に対応できる」というメリットがある一方で、「政府の解釈しだいで憲法の意味が変わってしまうのではないか」というデメリットも指摘されています。
そこで、日本では「改憲自体をもっとやりやすくすべきではないか」という議論が生まれています。
改憲を容易にするように仕組みは変更すべきなのでしょうか。
〈憲法改正の手続き〉3ステップと法律との違い
法律よりも手続きの要件が厳しい憲法は、3ステップの流れで改正となります。
という流れです。
(憲法改正は、両院それぞれで総議員の3分の2以上の賛成が必要です。「どちらか一方のみではない」という点は注意です。)
なお、法律の場合は国民投票がなく、出席議員の過半数の賛成で法律が制定される(衆参で意見が違った場合は、出席議員の3分の2以上の賛成で可決される)ので、憲法のほうが硬性であることが確認できます。
はたして、憲法は法律のように積極的に改正や追加をしていくべきでしょうか。
【※参考:憲法改正についての国の動き】: 自主憲法論・憲法調査会・憲法審査会
ここからは補足として、戦後の日本で「憲法改正」をめぐってどのような動きがあったのかを、簡単に確認しておきます。
〈自主憲法論と自由民主党〉
日本国憲法のベースはマッカーサー草案です。誤解を恐れずに言うとGHQによる憲法だと考えられます。
そこで、戦後の日本は自主憲法を作ろうと考えました。そのために日本が行ったことは大きく2つです。
1つは、保守派と呼ばれる人たちが集まり、憲法改正の発議を目指そうという動きです。
そのために作られた政党を自由民主党と呼びます。
(戦前の憲法を守るので保守派です。戦前の憲法にするためには憲法改正の必要があるので、憲法改正派は革新ではなく保守派になります。)
〈憲法調査会から憲法審査会へ〉
もう1つは、憲法改正のために組織を作るという動きです。
そのために作られた組織を憲法調査会と呼びます。
なお、憲法調査会は2回組織されて2回廃止されたという経過があります。(つまり、2025年現在、憲法調査会は存在しません。)
憲法調査会の1回目は1956年です。当時の鳩山一郎首相が内閣の中に作りました。
1回目の憲法調査会は、1964年にその役割を終えたとして廃止されています。
2回目は2000年です。憲法改正に向けて調査するため、今度は衆参両院に設置されました。
なお、2回目の憲法調査会は5年を目途に活動していたこともあり、2007年に憲法審査会として生まれ変わりました。
現在は常設的な機関として、主に憲法改正の原案を審理しています。
〈国民投票法と18歳以上の投票権〉
また、憲法改正については、国民投票法も制定され、国民投票の投票権は18歳以上の日本国民となりました。
【あわせて読みたい】
【※参考:日本国憲法の三大原理と2つの前提のまとめ】
このまとめで確認すること
・ 日本国憲法の三大基本原理
・ 憲法の前提①:最高法規性と憲法尊重擁護義務
・ 憲法の前提②:硬性憲法・解釈改憲・改正手続き
・ 戦後日本における憲法改正をめぐる動き
1.日本国憲法の三大基本原理
・ 国民主権 … 国の政治の最終的な決定権は国民にある(天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」として国事行為のみを行う)
・ 基本的人権の尊重 … 人々の権利は「侵すことのできない永久の権利」として保障され、その土台には「個人の尊重」がある
・ 平和主義 … 憲法前文で平和的生存権を掲げ、9条で「戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認」を定めている
2.憲法の前提①:最高法規性と憲法尊重擁護義務
・ 憲法は「国の最高法規」であり、他のすべての法律や命令よりも上位にある
・ 憲法尊重擁護義務を負うのは、国会議員・内閣・裁判官などの 「国家権力の側」 であり、憲法は国民ではなく 「国家権力を縛るためのルール」 である
3.憲法の前提②:硬性憲法・解釈改憲・改正手続き
・ 日本国憲法は「硬性憲法」であり、通常の法律よりも改正手続きの要件が厳しい
・ 自衛隊をめぐる議論などでは、条文を変えずに解釈を変える「解釈改憲」が行われてきた
・ 憲法改正の手続きは、
① 各議院の総議員の3分の2以上の賛成
② 国会による発議
③ 国民投票で過半数の賛成
の3ステップで行われる(法律は国民投票なしで、出席議員の過半数の賛成で成立)
4.戦後日本における憲法改正をめぐる動き
・ 日本国憲法のベースはマッカーサー草案であり、その後「自主憲法をつくるべきだ」という議論も生まれた
・ 憲法改正の是非をめぐり、保守政党(自由民主党)や、憲法調査会・憲法審査会といった組織が設置されてきた
・ 国民投票法の制定により、憲法改正の国民投票に参加できるのは 「18歳以上の日本国民」 とされている
覚える際の視点
覚え方の軸は、「三大原理」+「2つの前提」です。
・ 三大原理 … 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義
・ 前提① … 憲法は国の最高法規であり、国家権力を縛るルールである(最高法規性)
・ 前提② … 憲法は法律より改正しにくく、解釈を通じて現実に対応している(硬性憲法・解釈改憲)
このセットでおさえておくと、憲法の前提を体系的につかみやすくなります。