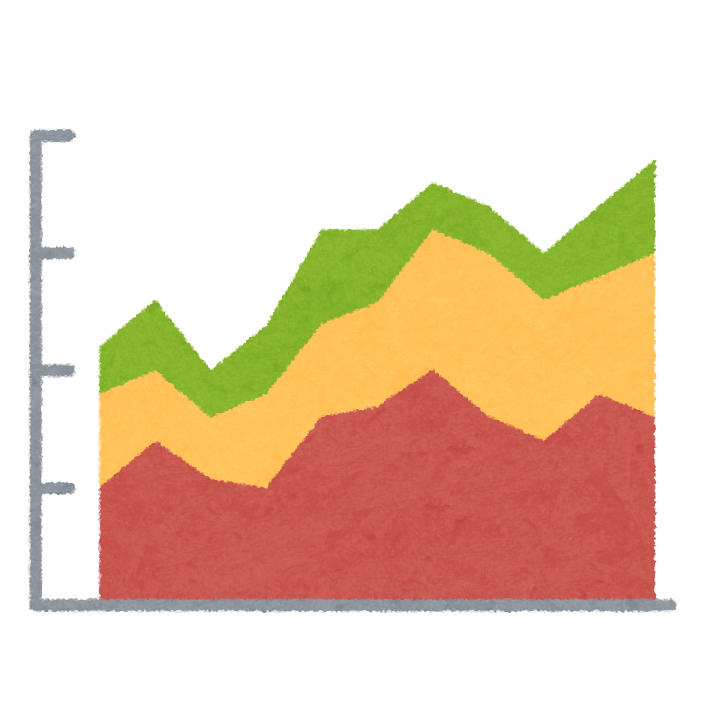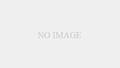高校生は大人でしょうか、それとも子どもでしょうか。また、なぜそのように判断することができるのでしょうか。
例えば、「成人式を行ったら大人」という意見は正しいのでしょうか。
中には、「一人暮らしができるようになったら大人」という意見があるかもしれませんが、そうだとしたら、両親と一緒に生活している30歳独身は子どもなのでしょうか。
逆に、一人暮らしをしている高校生がいたら、それは大人になるのでしょうか。
「お金を稼ぐことができれば大人」という意見も考えられますが、アルバイトでお金を稼いでいる高校生は大人ということになるのでしょうか。
逆に、両親がお金持ちで、両親の資産に頼りながら全く働いていない50歳は子どもなのでしょうか。
はたして、「高校生は大人か子どもか」という質問の答えはなんなのでしょうか。
【「青年期」とは】
「高校生を大人として捉えるか、子どもとして捉えるか」については、「青年期」という時期を考える必要があります。
青年期とは、簡単に言うと思春期のことを指します。そのため、青年期という時期を考える場合は、多くの高校生が直面する思春期について考えると分かりやすいです。
なお、青年期とは心理学などでよく登場しますが、一般的には高校生前後の発達過程のことを指します。
(ただし、現在は青年期が長期化する傾向にあり、広く捉えると30歳くらいまで青年期が続く人もいます。)
そもそも、「発達=機能の伸び」を指す言葉なので、高校生前後で様々な機能の伸びの見られる時期が青年期だと言えます。
【発達の3分類】
発達は身体的、精神的、社会的と大きく3つ考えられます。
例えば、身体的発達の1つとして、身体に男らしさ、女らしさが出てくることが挙げられます。(これを第二次性徴と言います。)
なぜ、青年期を第一次性徴ではなく第二次性徴と呼ぶのでしょうか。
そもそも性徴とは、「性別が分かる身体的特徴」を略したものです。
なお、身体面で性別を判別する機会は大きく2回あります。
1回目は生まれた瞬間です。生まれた瞬間に見た目で男性か女性か判別できます。
2回目は中学から高校生くらいの頃です。このころになると多くの男性は声変わりが見られる、多くの女性は乳房の膨らみが見られるなど、身体的に性別が分かる特徴が出てきます。
このような身体的特徴から性別を判断する際の1回目の特徴を「第一次性徴」と呼び、2回目の特徴を「第二次性徴」と呼びます。
そのため、高校生前後に見られる特徴の1つが第二次性徴だということになります。
また、精神的発達の1つとして、自我(=自分らしさ)がめばえます。
人間は一般的に身体的発達よりも精神的発達のほうが遅いので、カラダばかりが先に成長してしまい、ココロがカラダと同じように成長しません。つまり、ココロがカラダに追いつかないというわけです。そうすると、ココロはまだまだ子どもなのに、カラダは大人なので、ココロとカラダの成長が一致せずにイライラすることがあります。
この、ココロがカラダに追いつかず、イライラの時期を反抗期と呼びます。そして、このイライラの時期を乗り越えてココロとカラダが一致する状態を「自我のめざめ」と呼びます。
(なぜ、中高生の多くが親に対して反抗してしまうのか、それは、カラダは大人なのにココロが大人になりきれず、親がまるで子どものように中高生を扱ってしまうから、という説明ができます。)
また、社会的発達として、自分なりの人生観や世界観の創出なども見られます。
例えば、「ロマンチック」という言葉を説明しようとすると、どのような説明になるでしょうか。辞書的な意味では、「現実離れした感動」などとなりますが、恋愛している高校生なんかは、ロマンチックを「彼氏・彼女と一緒にいる時のトキメキ」などど、より具体的に自分なりの世界観を作ってくることがあります。
このような、自分なりの人生観や世界観を創出するのは、青年期に多いとされます。
【「青年期」の出現】
人は、子供 → 青年期 → 大人というように、青年期を経て子供から大人になります。
では、どうすれば子供から大人になることができるのでしょうか。
昔は、通過儀礼(イニシエーション)を経て大人になるとされました。
通過儀礼は「人生の節目にある儀式」という意味です。成人式や七五三などが通過儀礼にあたります。
ただし、成人式に参加したらその瞬間から子供から大人に切り替わるのでしょうか。そもそも成人式に参加しなかった人はどうなるのでしょうか。このような問いに答えることは難しくなってしまいます。
そこで、現在は子供から大人になるのに一定の学習期間(準備期間)があると考えられています。この準備期間のことを青年期と呼びます。
【青年期のとらえ方①(エリクソン・ルソー)】
青年期を言い換えると、どのように捉えることができるでしょうか。
この質問に歴代の多くの人が答えています。
エリクソンという人は、青年期は様々な経験などを積みながら「大人になるための猶予期間」であると考えました。
この猶予期間を「心理・社会的モラトリアム」と表現しました。つまり、中高生は猶予期間のうちに多くの経験を積むことが重要だという発想です。
また、ルソーという人は『エミール』という本で、「第二の誕生」という言葉を残しました。
第一の誕生はこの世に生まれたという意味での誕生、第二の誕生は自分自身の中で自我が芽生えたという意味での誕生を指します。
つまり、ルソーによると青年期は第二の誕生を経たことで大人になると捉えられます。(よく中学生や高校生である日突然、性格が豹変して大人びることがありますが、あの瞬間がまさしく第二の誕生だと捉えられます。)
【青年期のとらえ方②(ビューラー・ホリングワース)】
最近、周囲の人に否定的になった経験はあるでしょうか。
直近を振り返ってもたくさんあるかもしれません。友人や家族にあたってしまったことも1度や2度ではないと思います。
では、その周囲の人にはいつから否定的になっていたのでしょうか。
そして、どんな内容で否定的になっていたのでしょうか。
ビューラーという人は、反抗期は幼児のころと青年期の2回来ることから、青年期に見られる反抗期を「第二反抗期」と名付けました。
(ちなみに、幼児のころの反抗期を第一反抗期と呼びます。一般的に言われる「イヤイヤ期」が第一反抗期にあたります。)
第二反抗期のときに、様々な理由でイライラしてしまい、周囲に対して否定的になることが考えられます。
また、ホリングワースという人は、人間は生後1年前後で見られる母親の母乳から離れる「生理的離乳」に対して、青年期に親から精神的に独立する様子を「心理的離乳」と名付けました。
人によっては、心理的離乳がスムーズにできず、イライラにつながって周囲の人達に否定的になることが考えられます。
【青年期のとらえ方③(レヴィン)】
子供と大人をはっきりと区別することはやはり難しいものです。
そこで、もし子供と大人の割合を%で表すとどうでしょうか。そして、なぜその%だと考えられるのでしょうか。
現在の高校生は、何%程度大人になっていて、何%程度がまだ子どもと言えるのでしょうか。この質問に明確な答えを出すことは難しいですが、高校生を「100%子供」や「100%大人」というように断定するのも、また難しいと思います。この、子供と大人の境界にいる状態をレヴィンという人は「マージナルマン(境界人)」と表現しました。
このように、青年期は様々な面からとらえることができますが、青年期は高校生にとって、また、現代社会で生活する全ての人の人生にとってどのような意味があるのでしょうか。