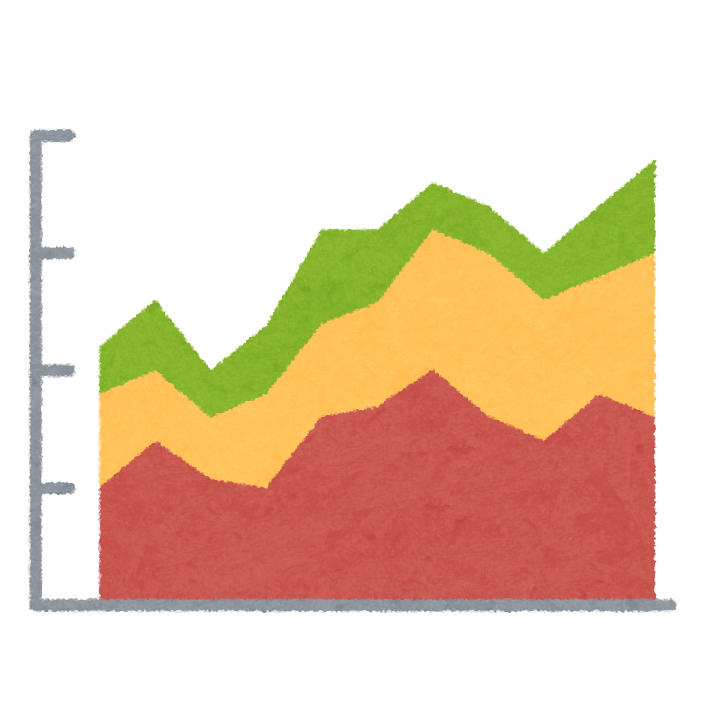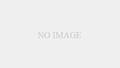【市場の失敗とは】
現代社会では、ある事情によって市場メカニズムが上手に働かない場合があります。
この状況を「市場の失敗」と呼びます。
市場の失敗として大きく4種類があります。
【独占と寡占】
数社が市場をコントロールしている状態を「寡占」と呼び、一社が市場をコントロールしている状態を「独占」と呼びます。
独占や寡占の市場では、プライスリーダーに他社が従うとされます。
つまり、力があって価格を設定できる企業をプライスリーダーと呼び、プライスリーダーの価格に他の企業がついていくことで価格が決定されていきます。
(このとき、プライスリーダーが設定した価格を管理価格と呼びます。)
また、管理価格には他の企業もついていかないと管理価格を設定した企業に負けて儲からなくなってしまうため、独占や寡占の市場では価格競争が発生しにくくなり、結果として商品の価格が固定的かつ下がりにくくなってしまいます。
この現象を「価格の下方硬直性」と呼びます。
そして、独占や寡占の市場では、価格が下がりづらいため、価格ではない面で他の企業に勝とうとして競争が激化します。
この競争を「非価格競争」と呼びます。
(非価格競争では、広告やアフターサービスなどで差別化を図ることがあります。)
ただし、日本では法律で独占や寡占についてルールを設けており、その法律を独占禁止法と呼びます。
なお、独占や寡占の発生要因の1つは「規模の経済性(スケールメリット)」と呼ばれるもので、事業の規模が大きくなるほど、商品1つあたりの生産費用が安くなることで、他の企業と比較して有利になる状態を指します。
【公共財】
稼げないけどないと困るものを公共財と呼びます。そのため、公共財の提供は、利潤追求を目指す企業による提供は難しく、基本的に市役所などの公共サービスが行うことになっています。
なお、公共財は2つの要素を持ち合わせています。
それが「非競合性」と「非排除性」です。
非競合性は多くの人々が同時に利用可能である(それをいくら使っても減らない)こと、非排除性は誰でも利用を制限されない(お金を払った人だけしか使えないなどのような状況が起きない)ことを指します。
灯台や公園などの公共財は、多くの人々が同時に利用可能であり、誰でも利用を制限されません。
【情報の非対称性】
商品の買い手と商品の売り手では、持っている情報に差があります。そのような、情報に差がある状態を「情報の非対称性」と呼びます。
簡単に言うと、情報の少ない買い手は、情報の多い売り手に翻弄されてしまい、本来の適正価格よりも高い価格で買ってしまうことがあり得る、という話です。
【外部経済・外部不経済】
なにもしていないのにお店の売上が増えるなどトクする状態を「外部経済」と呼びます。
また、なにもしていないのにお店の売上が減るなどソンする状態を「外部不経済」と呼びます。
この記事の詳細版は以下でチェックできます。